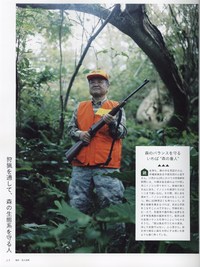2008年06月24日
県議会議員、任期満了。
平成8年6月に初当選して以来、3期12年の県議としての議員活動が、本日無事終了しました。
昨日の、平成20年 沖縄全戦没者追悼式参列が、最後の公務となりました。
その追悼式での、正午からの黙とうに続く、沖縄県遺族連合会会長の仲宗根義尚氏の、「是非、わが国の為に散華された英霊の眠る靖国神社参拝をお願いしたい」と、福田内閣総理大臣に対して強く要請する言葉が、とても印象的でした。
さて、平成8年に初当選を果たした、いわゆる県議会議員としての同期には、当時保革合わせて19名いました。
しかし去った6月8日の県議選で、4期連続で当選を果たした同期はたったの3名しかおりません。
自民の池間淳・浦崎唯昭と公明の糸洲朝則です。
同期として、3氏のこれからの更なる活躍を期待します。
12年間を振り返ってみると、最初の2ヶ年は大田昌秀革新県政でした。
当時県には、2015年までに沖縄におけるすべての米軍基地を返還させるという『基地返還アクションプログラム』、返還跡地には国際都市を築き上げるという国際都市形成構想がありました。
沖振法などの法的な裏付けが全くない、単なる沖縄県のみの絵に描いた餅でしかない計画でしたが、マスコミはこれを取り上げ、議会でも時間をかけて議論を積み重ねていたものです。
私はというと、わが国の外交と防衛の基軸である日米安保にまったく言及しない同構想に対し、一貫して反対しておりましたが、当時はこれに反対することはすなわち非県民であるかのような報道がなされており、私もいろいろと揶揄されていたことが、印象に残っています。
さらに大田知事は、一坪反戦地主と連動して米軍用地使用の代理署名拒否を貫いたため、政府は衆参両院で9割近くの圧倒的多数をもって軍用地特措法を成立させ、これにより沖縄県は『地権者』というカードを完全に失うことになりました。
私は日米安保を認める立場にありますが、以前の記事にも書いたように『交渉』ということを考えたとき、この法律の成立を招いたことは、県民に対しての大きな失政である、と考えております。
その後大田知事はSACOでも土壇場で反対を唱えたため、沖縄県は完全に行き詰ってしまいました。
このような沖縄を覆う閉塞感の中で、平成10年11月、私の県議3年目の秋に、『解釈より解決を!』をキャッチフレーズに、県民の期待を一身に集めて稲嶺恵一県政が誕生しました。
しかし稲嶺県政においても結局は8年間解釈ばかりに終始し、世論の動向に気を配るばかりで、SACO関連基地問題は何一つ解決することなく、現在に至るまで根本的な解決は図れておりません。
これは、国会議員をはじめ、権限を持っている政治家が『火中の栗を拾う』という気概を持ち合わせていないことが、最も大きな原因であると私は考えています。
SACOが動き始めれば、政府による莫大な公共投資がなされます。
そこには、新たなビジネスチャンスも、大きな雇用も、生まれます。
例えば、普天間の跡利用の問題。
通常、返還された基地の跡利用は各々の地方自治体が行います。
しかし普天間基地に関しては、政府が責任をもって行うことがすでに決められています。
例えば那覇市天久は、返還から利用までには10年以上の時間を要しましたが、国が事業をやるとなると、その年月も掛かる金額も大幅に圧縮されることが期待できます。
他にも、返還に伴うチャンスは多々あります。
これをチャンスにして足元からしっかりと組み上げていくことが出来れば、停滞している沖縄県経済の活性化が図れるだけでなく、沖縄県の更なる発展・飛躍へとつながる大事業になるであろうことは確実です。
そういう意味でも、これからの10年間は、沖縄にとっての大きなチャンスとなりますし、もしかしたら最後の飛躍のチャンスであるかもしれません。
解釈ではなく、責任をもって『基地問題』の本質的な解決を図り、沖縄県全体を良くしていくために、私はこれからもしっかりと頑張っていきます。
県議会議員としての活動はこれで終わりになりますが、これからは『火中の栗を拾う』ために、衆院選沖縄県第3選挙区から、次期衆院選の当選に向け、引き続き政治活動を続けていきます。
県民の皆様の暖かいご理解をお願いいたします。
昨日の、平成20年 沖縄全戦没者追悼式参列が、最後の公務となりました。
その追悼式での、正午からの黙とうに続く、沖縄県遺族連合会会長の仲宗根義尚氏の、「是非、わが国の為に散華された英霊の眠る靖国神社参拝をお願いしたい」と、福田内閣総理大臣に対して強く要請する言葉が、とても印象的でした。
さて、平成8年に初当選を果たした、いわゆる県議会議員としての同期には、当時保革合わせて19名いました。
しかし去った6月8日の県議選で、4期連続で当選を果たした同期はたったの3名しかおりません。
自民の池間淳・浦崎唯昭と公明の糸洲朝則です。
同期として、3氏のこれからの更なる活躍を期待します。
12年間を振り返ってみると、最初の2ヶ年は大田昌秀革新県政でした。
当時県には、2015年までに沖縄におけるすべての米軍基地を返還させるという『基地返還アクションプログラム』、返還跡地には国際都市を築き上げるという国際都市形成構想がありました。
沖振法などの法的な裏付けが全くない、単なる沖縄県のみの絵に描いた餅でしかない計画でしたが、マスコミはこれを取り上げ、議会でも時間をかけて議論を積み重ねていたものです。
私はというと、わが国の外交と防衛の基軸である日米安保にまったく言及しない同構想に対し、一貫して反対しておりましたが、当時はこれに反対することはすなわち非県民であるかのような報道がなされており、私もいろいろと揶揄されていたことが、印象に残っています。
さらに大田知事は、一坪反戦地主と連動して米軍用地使用の代理署名拒否を貫いたため、政府は衆参両院で9割近くの圧倒的多数をもって軍用地特措法を成立させ、これにより沖縄県は『地権者』というカードを完全に失うことになりました。
私は日米安保を認める立場にありますが、以前の記事にも書いたように『交渉』ということを考えたとき、この法律の成立を招いたことは、県民に対しての大きな失政である、と考えております。
その後大田知事はSACOでも土壇場で反対を唱えたため、沖縄県は完全に行き詰ってしまいました。
このような沖縄を覆う閉塞感の中で、平成10年11月、私の県議3年目の秋に、『解釈より解決を!』をキャッチフレーズに、県民の期待を一身に集めて稲嶺恵一県政が誕生しました。
しかし稲嶺県政においても結局は8年間解釈ばかりに終始し、世論の動向に気を配るばかりで、SACO関連基地問題は何一つ解決することなく、現在に至るまで根本的な解決は図れておりません。
これは、国会議員をはじめ、権限を持っている政治家が『火中の栗を拾う』という気概を持ち合わせていないことが、最も大きな原因であると私は考えています。
SACOが動き始めれば、政府による莫大な公共投資がなされます。
そこには、新たなビジネスチャンスも、大きな雇用も、生まれます。
例えば、普天間の跡利用の問題。
通常、返還された基地の跡利用は各々の地方自治体が行います。
しかし普天間基地に関しては、政府が責任をもって行うことがすでに決められています。
例えば那覇市天久は、返還から利用までには10年以上の時間を要しましたが、国が事業をやるとなると、その年月も掛かる金額も大幅に圧縮されることが期待できます。
他にも、返還に伴うチャンスは多々あります。
これをチャンスにして足元からしっかりと組み上げていくことが出来れば、停滞している沖縄県経済の活性化が図れるだけでなく、沖縄県の更なる発展・飛躍へとつながる大事業になるであろうことは確実です。
そういう意味でも、これからの10年間は、沖縄にとっての大きなチャンスとなりますし、もしかしたら最後の飛躍のチャンスであるかもしれません。
解釈ではなく、責任をもって『基地問題』の本質的な解決を図り、沖縄県全体を良くしていくために、私はこれからもしっかりと頑張っていきます。
県議会議員としての活動はこれで終わりになりますが、これからは『火中の栗を拾う』ために、衆院選沖縄県第3選挙区から、次期衆院選の当選に向け、引き続き政治活動を続けていきます。
県民の皆様の暖かいご理解をお願いいたします。
Posted by オド 亨 at 18:28│Comments(1)
│沖縄県政に関すること
この記事へのコメント
3期12年の県議会活動お疲れ様でした
あっという間の波瀾万丈の県政運用でしたね
今後は国政の場に置いて沖縄県の歴史的文化的
立場をふまえて国民の為に活躍することを期待します
応援します!
あっという間の波瀾万丈の県政運用でしたね
今後は国政の場に置いて沖縄県の歴史的文化的
立場をふまえて国民の為に活躍することを期待します
応援します!
Posted by イチャリバチョウダイ at 2008年06月25日 21:43